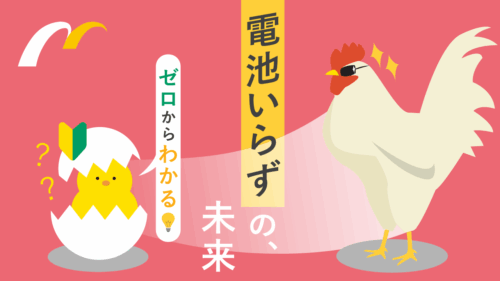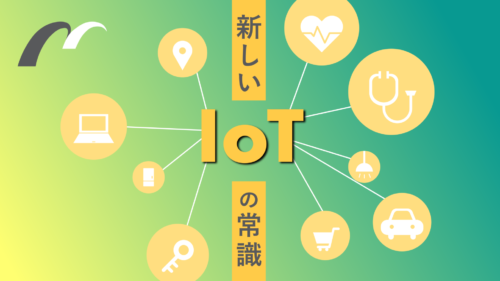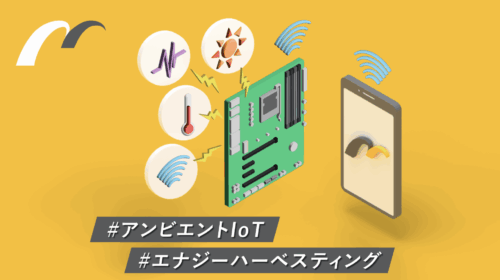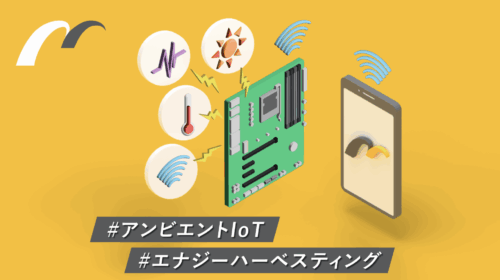ゼロからわかる環境発電入門(4)センシングと無線通信
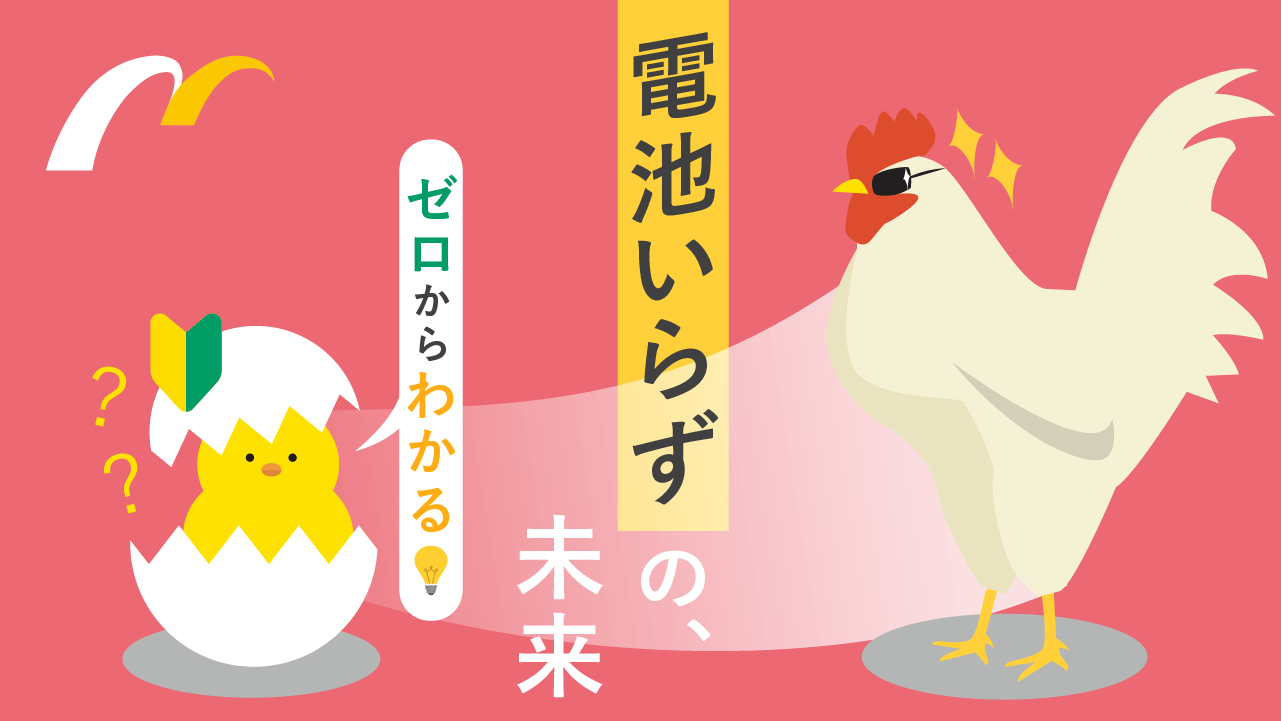
こんにちは。ムセンコネクト三浦です。
環境発電(エネルギーハーベスト)は、身の回りにある微小なエネルギー(光、熱、振動など)を「収穫」し、電力に変換して利用する技術のことです。
本連載では、この「環境発電・エネルギーハーベスト」を、複数回に分けて基礎からわかりやすくご紹介していきます。
前回は環境発電デバイスの電力の「生成」から「利用」までの5ステップを紹介しました。
今回は、その最終段階である「エネルギーの利用」に焦点を当てて解説します。
特に環境発電を利用したIoTデバイスを開発する際に重要となる「センシング」と「無線通信」を中心に紹介します。
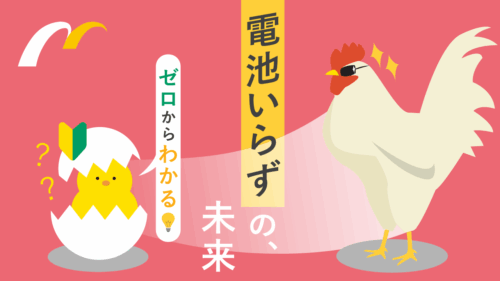
アンビエントIoTデバイスのセンシングと無線通信
環境発電を利用するIoTデバイス(以下、アンビエントIoTデバイス)は、その性質上、限られた電力で最大のパフォーマンスを発揮する必要があります。そのため、「いかに電力を節約しながら、必要な情報を送信するか」が設計のポイントになります。
具体的には、以下の2つの要素が重要です。
- 低消費電力なセンシング : 必要なデータを効率良く取得する
- 低消費電力な無線通信 : 必要なデータを最小限の電力で相手に送信する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
低消費電力なセンシング
センサーの選定のポイント
アンビエントIoTデバイスでは、センサー自体が消費する電力や、センサーを起動させるための時間が重要になります。
- 消費電力が小さいこと
- わずかな電力でも動作するように、できるだけ消費電力が小さいセンサーを選択します。
- スタートアップ時間が短いこと
- センサーが計測を開始できるまでの時間が短いほど、全体の電力消費を抑えられます。スリープ状態から素早く復帰できるのが理想的です。
- 精度
- 省電力であっても、必要な精度がなければ意味がありません。また、過剰な精度を求めて消費電力が上がってしまうのも避けたいところです。環境や用途に合わせて適切な精度のものを選択します。
よく利用されるセンサーの種類
アンビエントIoTデバイスでは以下のようなセンサーがよく利用されます。
- 温度センサー
-
周囲の温度を計測します。
建物の空調管理、食品・薬品の品質管理、工場機械の異常検知などに利用します。 - 湿度センサー
-
空気中の湿度を計測します。
温湿度管理、結露防止、農業分野などに利用します。 - 照度(光)センサー
-
光の明るさを計測します。
スマート照明制御、植物の生育環境モニタリングなどに利用します。 - 加速度センサー
-
物体の傾きや振動を検知します。
姿勢検知、機械の稼働監視、橋梁などの構造物の異常検知などに利用します。 - CO2センサー
-
空気中の二酸化炭素濃度を計測します。
換気管理、居住空間の快適性維持などに利用します。
アンビエントIoTデバイスで利用する際のコツ
- 必要なデータだけを取る
-
不要な電力消費を抑える為、不要な情報を取得しないようにセンサーの設定を最適化します。サンプリングの頻度も、必要な情報量に合わせて調整します。
- 間欠動作
-
常にセンサーを稼働させるのではなく、必要な時だけ起動し、データを取得したらすぐにスリープモードに戻す「間欠動作」を徹底します。多くのアンビエントIoTデバイスは、この間欠動作によって電力消費を劇的に抑えています。
- 実物で測る・試す
-
センサのデータシートには動作状態毎の大まかな消費電流は載っていますが、1回のセンシング動作にかかる電力消費量の詳細を知ることはできません。実物を動かしてみて電力消費量を測る必要があります。
低消費電力な無線通信
センシングしたデータを外部に送信する「無線通信」は、IoTデバイスの中でも特に電力を消費する部分です。
そのため、アンビエントIoTデバイスでは、用途に応じて低消費電力な無線通信方式を選ぶことが非常に重要です。
無線通信選定のポイント
- 消費電力
- できるだけ省電力なものを選定します。
各通信規格の種類や各社の通信モジュールによっても消費電力が異なります。
- できるだけ省電力なものを選定します。
- 通信距離
- デバイスと受信機の間の距離はどのくらいか? 送信電力が高いほど電波が遠くに飛びますが消費電力も高くなります。
- データ量と頻度
- 1回の送信で送れるデータ量はどのくらいか? 送信するデータ量が大きい程消費電力も大きくなります。
送信できるデータ量に制限がある通信規格もあります。
- 1回の送信で送れるデータ量はどのくらいか? 送信するデータ量が大きい程消費電力も大きくなります。
- システム全体を構築する手間とコスト
- 専用のゲートウェイやネットワークインフラが必要か、既存のスマートフォンやパソコンを利用できるか、システム全体で考えます。
よく利用される無線通信規格
アンビエントIoTデバイスでは以下の無線通信がよく利用されます。
- Bluetooth LE (BLE)
-
- 2.4GHz帯を利用した非常に低消費電力な通信方式です。
- スマートフォンやパソコンとの連携が容易です。
- 10m~100m程度の近距離通信に適しています。
- 特にビーコン方式(ブロードキャスト方式)でセンサデータを送信する方式は安定した電力供給が約束されていないアンビエントIoTデバイスに向いていると言えます。
- EnOcean (エンオーシャン)
-
- 920MHz帯を利用した非常に低消費電力な通信方式です。
- 30m~300m程度の近距離から中距離に適しています。
- スイッチ押す力で発電する発電モジュールと一緒にユニット化されて販売されていたりします。
- スマートフォンやパソコンと連携する為には受信装置が別途必要になります。
- Sigfox (シグフォックス)
-
- 920MHz帯を利用した低消費電力で長距離通信が可能な通信方式です。
- 数km先のSigfox基地局まで送信することが出来ます。※Sigfoxの回線契約が必要です。
- Sigfox基地局は人口カバー率95%で、ゲートウェイなどを自分で設置する必要がありません。
- 1回に11バイトしか送信できないという制約があります。
- Bluetooth LEやEnOceanと比べると大きな電力が必要です。
アンビエントIoTデバイスで利用する際のコツ
- 無線通信機能付きマイコンを選定
-
センサーをセンシングするマイコン機能と無線通信ICが一体になったものを利用すると、別体になっているものよりも消費電流の効率がよく、コストも抑えられます。
- スリープモードの活用
-
無線モジュールは、通信時以外は深いスリープモードに入れ、消費電力を極限まで抑えます。またスリープを解除してから動き出すまでのスピードが早いものを利用します。
- センシングしたデータを加工して送信
-
センシングしたデータが大量な場合は、デバイス側で加工したり、アルゴリズム判断をしてから送信することを考えましょう。大量のデータを無線通信して送信するより、マイコン内部で処理した方が結果的に電力を抑えることができる場合があります。
環境発電を利用したIoTデバイス(アンビエントIoTデバイス)の開発は、センサーと無線通信の選択にその成否が大きくかかっています。
限られたエネルギーを最大限に活かすためには、あらゆる段階で「省電力」を徹底する視点が不可欠です。
環境や用途に最適なセンサーと通信方式を選び、それらを効率的に制御する設計を行うことで、メンテナンスフリーで長期間稼働する魅力的なIoTデバイスが実現します。
次回も、環境発電・エネルギーハーベスト技術のポイントを紹介していきます。