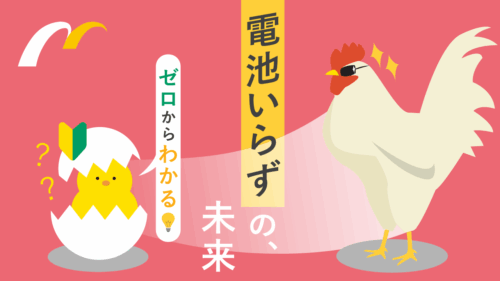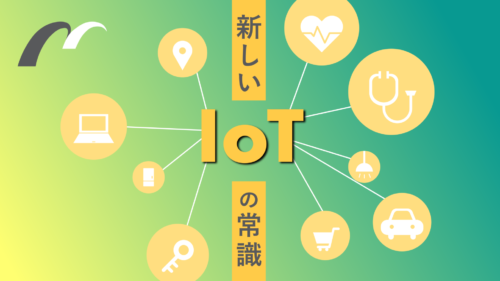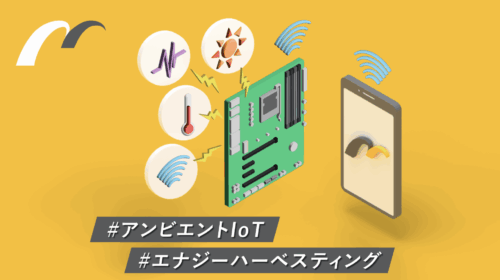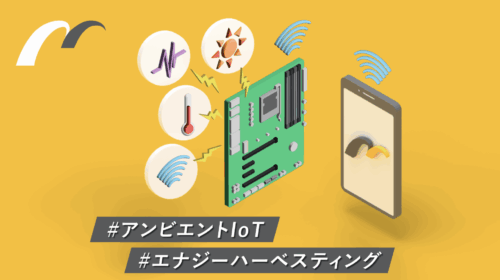ゼロからわかる環境発電入門(3)環境発電の構成・5つのプロセス
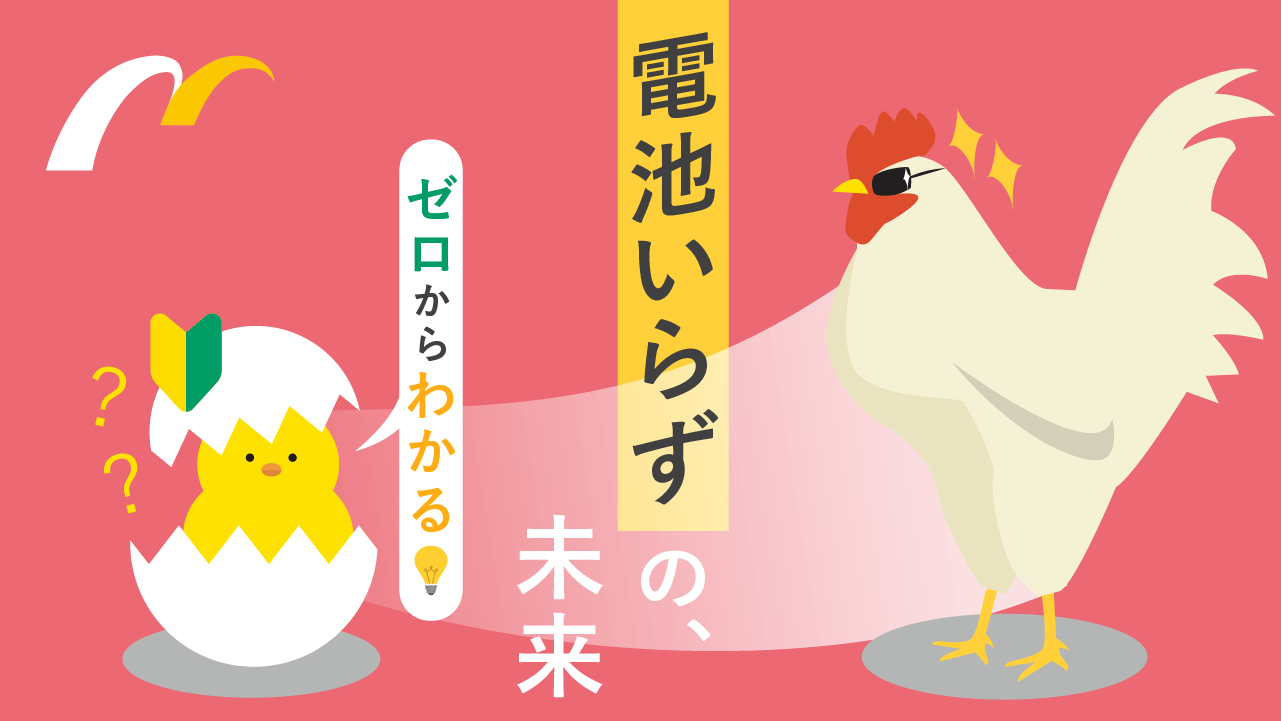
こんにちは。ムセンコネクト三浦です。
環境発電(エネルギーハーベスト)は、身の回りにある微小なエネルギー(光、熱、振動など)を「収穫」し、電力に変換して利用する技術のことです。
本連載では、この「環境発電・エネルギーハーベスト」を、複数回に分けて基礎からわかりやすくご紹介していきます。
第3回目の今回は、環境発電(エネルギーハーベスト)デバイスが実際にどのように電力を生成し、利用できる形にするのか、その具体的な構成・ステップを5つの段階に分けて解説していきます。
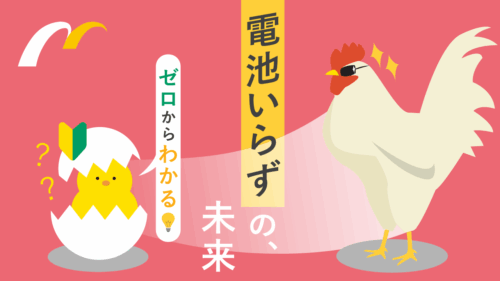
環境発電デバイスの電力フロー:5つのステップ
環境発電デバイスが環境エネルギーを捉えて利用するまでの流れは、大きく分けて以下の5つのステップで構成されます。
- エネルギーの生成(Genaration)
- エネルギーの変換(Conversion)
- エネルギーの貯蔵(Storage)
- エネルギーの配電(Distribution)
- エネルギーの利用(Utilization)
この各ステップを最適化することが、高効率で安定した環境発電デバイス開発の鍵となります。

ステップ① エネルギーの生成:電力を作り出す・収集する
最初のステップは、私たちの周りにある未利用のエネルギーをハーベスト(収集)することです。

- どんな環境で?
-
デバイスを設置する場所(屋外、屋内、工場内、人体など)のエネルギー源を特定します。太陽光が豊富な場所か、常に熱が発生する場所か、振動が多い場所か、電波が飛んでいる場所か、など。
- どんな方式で?
-
その環境で最も効率的にエネルギーを拾える「発電方式」を選定します。例えば、屋外なら太陽光発電、工場なら熱電発電、交通量の多い場所なら圧電発電といった具合です。
- どんな発電素子を利用して?
-
選定した方式に対応する「発電素子(ハーベスター)」を選びます。太陽電池セル、熱電変換素子、圧電素子、レクテナなどがこれにあたります。
この段階では、対象とする環境で「最も安定して、かつ最大量のエネルギー」を生成できる組み合わせを見つけることが重要です。発電素子の選定は、デバイス全体の性能を大きく左右します。
ステップ② エネルギーの変換:電力を扱いやすいように加工する
環境発電素子で生成された電力は、そのままでは使いにくい場合がほとんどです。交流だったり、電圧が低すぎたり高すぎたり、非常に不安定だったりします。
このステップでは、不安定な「電力」を、次の貯蔵段階で扱いやすいように「加工」します。

- 整流回路
-
交流で発電された電力を、直流に変換します。
- 昇圧/降圧回路
-
電圧が足りない場合は昇圧(高くする)、高すぎる場合は降圧(低くする)して、適切な電圧に調整します。
このステップでの「電力変換効率」がデバイスの性能を大きく左右します。いかに少ないロスで、不安定な電力を安定した直流電力に変換できるかが、回路設計の腕の見せ所です。専用のPMIC (Power Management Integrated Circuit) と呼ばれるICが重要な役割を果たします。
ステップ③ エネルギーの貯蔵:電力を小さなダムにためる
ステップ②で変換・安定化された電力は、まだ非常に微弱な場合が多く、後段の処理(センサー測定や無線通信など)を直接動かすには力不足です。
そこで、一時的に電力をためておく「ダム」のような役割を果たすのが、この貯蔵ステップです。蓄電デバイスには主にコンデンサと二次電池を利用します。

- コンデンサ(キャパシタ)
-
瞬時に大電流を放出できますが、蓄電容量が小さいのが特徴です。蓄電容量が小さい分、短い時間で電力を貯めることができますが、使う時もすぐに電力を使い切ってしまう為、間欠的に動作するデバイスに適しています。
- 二次電池(リチウムイオン電池、LTO電池、全固体電池など)
-
蓄電容量が大きく、長時間の電力供給が可能です。蓄電容量が大きい分、電力が貯まるまで時間がかかります。電池寿命や充電・放電特性を考慮する必要があります。
デバイスが必要とする電力量や動作頻度に応じて、最適な蓄電デバイスを選択します。特に、環境発電の不安定な電力をいかに効率良く、そして長寿命に蓄えられるかが重要です。
ステップ④ エネルギーの配電:ダムから必要な場所へ電力を流す
蓄電デバイスに十分な電力が貯まったら、それを後段のセンサーや通信モジュールへ「配電」します。

- 電圧レギュレータ
-
後段の回路が必要とする電圧に調整して供給します。
- 電源ON/OFF制御
-
必要な時だけ後段の回路に電力を供給し、無駄な消費電力を抑えます。例えば、一定量の電力が貯まるまで待機し、一気にセンシングと通信を行う「間欠動作」が一般的です。
このステップでは、いかに効率良く、そして無駄なく電力を供給するかが問われます。
特に、瞬間的に大きな電力を必要とする無線通信のタイミングに合わせて電力を「送り出す」制御が重要になります。
ステップ⑤ エネルギーの利用:集めた電力で「仕事」をする
最後のステップは、配電された電力を使ってIoTデバイスが「本来の仕事」を行うことです。

- 環境情報のセンシング
-
温度、湿度、光、圧力、振動、音、人の有無など、様々な環境情報をセンサーで測定します。電力消費を抑えるため、必要最低限の時間だけセンサーを稼働させる工夫が重要です。
- センシングデータの無線通信
-
収集したデータをBluetooth Low Energy (BLE)、EnOcean、Sigfoxなどの低消費電力無線通信技術で受信機やゲートウェイに送信します。無線通信は非常に電力を消費するため、送信頻度や送信距離、データ量を最適化することが不可欠です。
このステップでは、デバイス全体の「低消費電力設計」が最も重要になります。いかに少ない電力で、必要な情報を送信できるかが、環境発電デバイスの実用性を決定づけます。
また、無線通信を受信する側も含めたシステム構成を考えた上で、最適な無線通信を選択する必要があります。
環境発電デバイスの開発は、ただエネルギーを「生成」するだけでなく、その後の「変換」、「貯蔵」、「配電」、そして「利用」の全段階において、いかに効率を追求し、電力消費を抑えるかが問われる総合的なエンジニアリングです。
これらの5つのステップの最適化を追求することで、私たちの身の回りにある小さなエネルギーが、IoTデバイスを半永久的に動かすことができ、「電源コード不要・電池交換不要・充電不要」な世界の実現につながっていきます。
今回は環境発電デバイスの電力の「生成」から「利用」までの5ステップを紹介しました。
次回は、その最終段階である「エネルギーの利用」に焦点を当てて解説します。特に環境発電を利用したIoTデバイスを開発する際に重要となる「センシング」と「無線通信」を中心に紹介します。